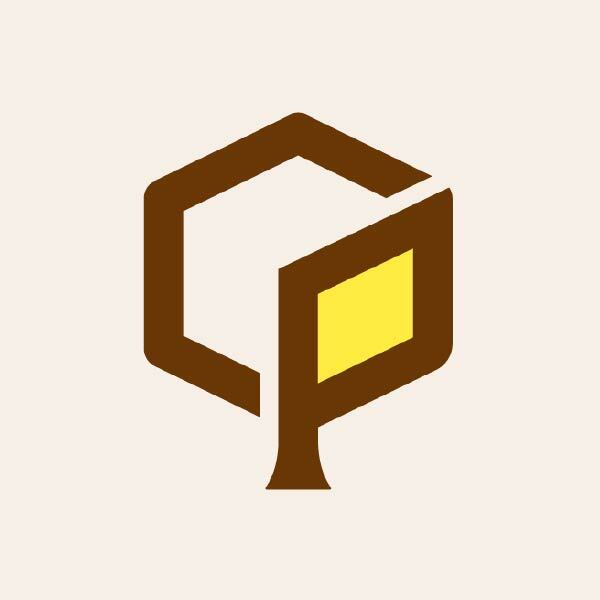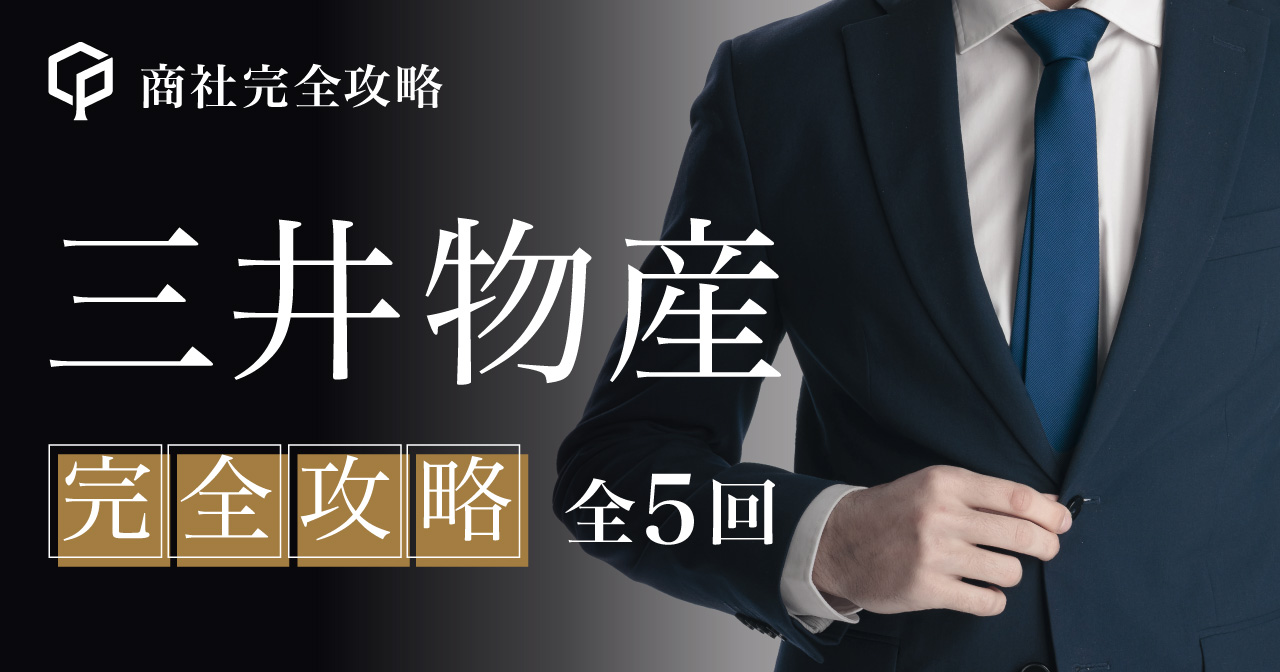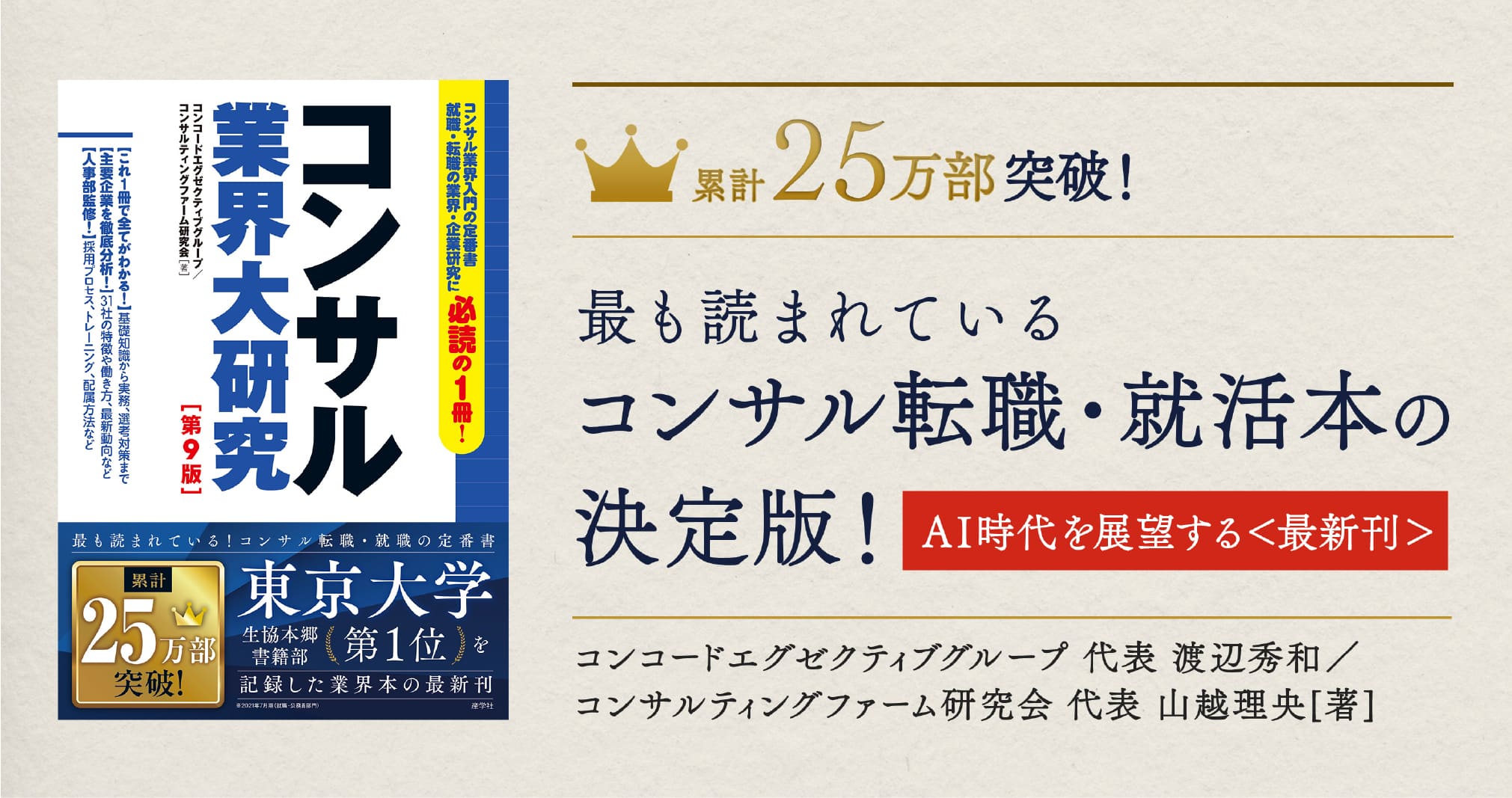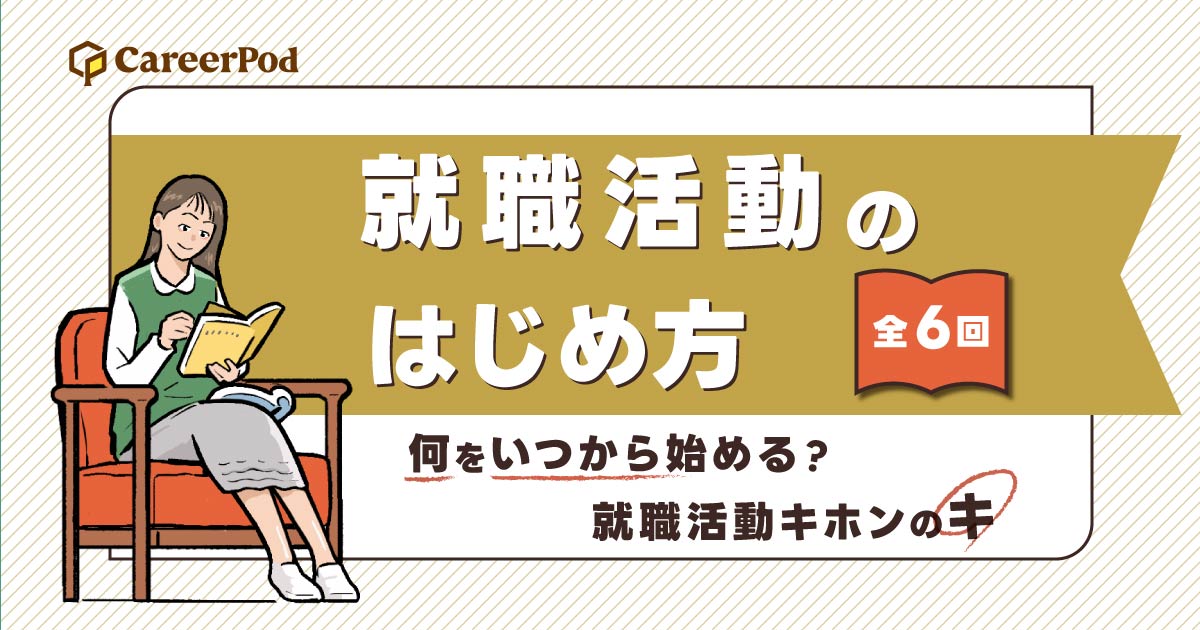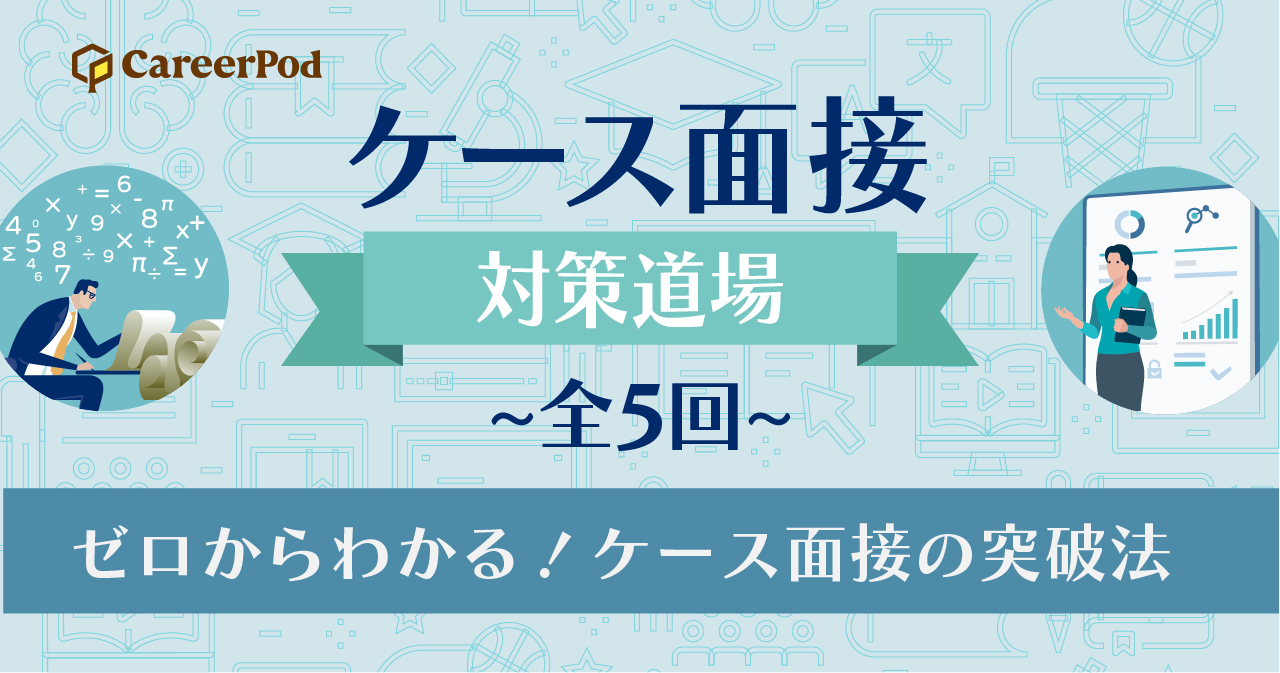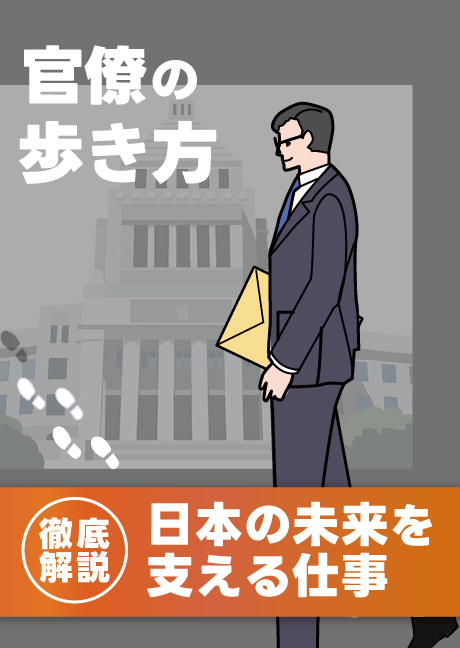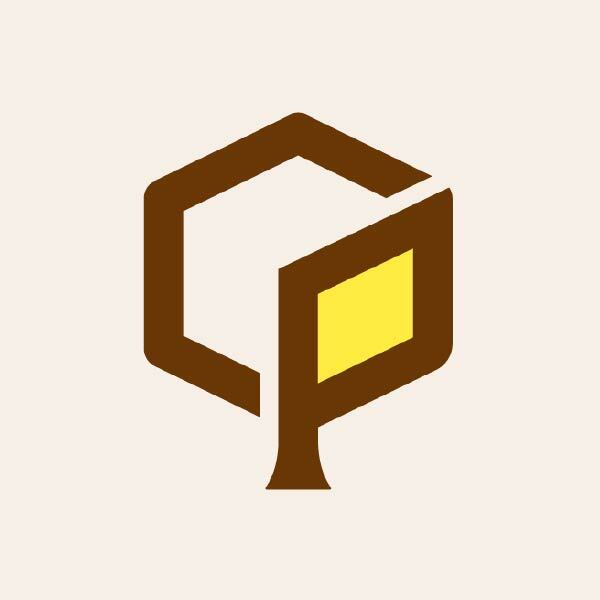
.jpg)
第4回 官僚のキャリアと収入
前回までは、官僚の仕事内容や各省庁が扱うテーマの違いについて紹介してきました。その上で気になるのは、「入省後どのようなキャリアを歩むことになるのか?」「具体的にはどのくらいの収入が得られるのか?」といった点ではないでしょうか。
そこで今回は、省内でのキャリアパスと、役職別の収入、代表的なネクストキャリアについてご紹介します。
省内でのキャリアパス
入省後の代表的なキャリアパスについては、以下の通りです。
係員(1~3年目)
政策の立案や実行に必要な資料集めやデータ整理、関係者との連絡などの仕事を通じて、「情報を正確にまとめる力」や「調整力」を身につけていきます。最初は地道な仕事が多いですが、仕事の流れを学び、官僚としての土台を築く大切な時期です。
係長・主査(4~6年目)
小さなチームのまとめ役として、後輩に仕事を割り振ったり、自分の意見をまとめて上司に伝えたりする機会が増えます。予算の編成や国会対応などの責任のある仕事を任されるようになり、楽しくなってくる時期でしょう。
課長補佐(7年目以降)
課のサブリーダーとなり、省内外の関係者との調整や、部下のマネジメントも重要な仕事になります。政策の一番のエキスパートとなることが求められるため、自分の考えたアイデアが政策として形になる手応えを、最も実感できるポジションです。
室長・課長(20年目以降)
担当分野が広くなり、全体を俯瞰しながら組織を動かす立場になります。省内外の重要な会議で議論をリードしたり、国会議員やメディアへの対応などプレッシャーのかかる場で矢面に立ったりと、政策内容にダイレクトに影響を及ぼす、霞が関の中枢を担う重要な役割です。
部長・審議官/局長(30年目以降)
複数の課を横断して、政策全体の大枠を最終決定して指揮をとる役割を担います。国会答弁や国際交渉では、省を代表して発言する機会も多いでしょう。こうした役職は省内の同期でも限られた人しか到達できないですが、政策実現の責任者としての重みと充実感を味わえる立場と言えます。
事務次官
各省の実質的トップであり、大臣を補佐しながら省全体の方向性と戦略を描く役割を担います。「国家としてどうあるべきか」を考えながら、省のあらゆる意思決定に深く関わるため、国家の未来を背負う責任の重さがある分、非常に大きなやりがいを感じられる職務でしょう。省に一つしかないポストのため、省内同期の中では基本的に一人しか到達できない“霞が関キャリアの頂点”です。
このように、様々な実務を経験するうちに、政策をつくる力、調整力、チームを導くリーダーシップといったスキルが磨かれて、だんだんと組織の中核を担う機会が増えていくのです。
また、上記は本省での役職ですが、官僚のキャリアパスでは、省外で幅広い経験を積むことで視野を広げる機会にも恵まれています。たとえば地方の支局・地方自治体や他省庁、海外の大使館・国際機関への出向の機会もあります。また、入省10年目までの若手のうちに希望すれば、人事院の制度を利用して国内外の大学院へ留学することも可能です。
役職別の収入
国家総合職の収入は、経験年数と役職に応じて上がっていきます。以下の表は、役職ごとの年収の目安をまとめたものです。

係員~課長補佐までの役職では、超過勤務手当(いわゆる残業代)が支給されるため、部署の忙しさによっては、実際の年収がもっと高くなることもあります。室長・課長以上の管理職に昇進すると、基本給が大きく上がる代わりに、残業代は支給されなくなります。
また、ごく一部の人しか就けない局長や事務次官のような役職では、年収は1,800万円以上にもなり、民間企業の役員クラスに匹敵する水準に到達できるでしょう。
代表的なネクストキャリア
省内での昇進を目指す場合、部長級や局長級といった上位のポストは数が少ないため、課長級以降、次のポストに進める人はごくわずかです。そのため、50代前半の時期に早期退職・再就職を選ぶ方と、定年まで勤め上げた後に再就職する方に分かれます。
再就職先は省庁によって違いはありますが、民間企業の役員、業界団体の理事、独立行政法人など国の関連団体の役員、大学・研究機関の理事などが主なポストです。このようなポストに就くことで、長年にわたり行政で培った専門知識や人脈を活かし、行政と民間の橋渡し役を担います。
また、近年では若手の転職も増えています。特に、官僚として磨いた分析力や調整力などを活かしやすいコンサルティングファームへの転職は多いです。そのほかにも、より住民に近い立場で働きたいという思いから地方自治体へ転職する方や、自らが政策決定の主体となって社会を動かしたいという思いから政治家へ転身する方など、行政での経験を活かしたキャリアチェンジをする方もいます。
さらに最近は、中央省庁や業界団体とのコミュニケーションを担える人材が民間企業で求められているため、渉外などを担う企画職に転職する方も増えてきています。
まとめ
今回は、官僚として歩む昇進ルートと役職別の収入、ネクストキャリアについてご紹介しました。
官僚のキャリアは、係員時代の地道な仕事からスタートしますが、経験を重ねるごとに政策立案や組織運営の中心を担うようになり、それに応じて収入も上がっていきます。加えて、仕事で培ったスキルや経験を活かし、ネクストキャリアにおいても多岐にわたる分野で活躍できる職業なのです。
次回は「官僚になるには?」と題して、官僚を目指す上でクリアすべき選考プロセスについて、具体的に解説していきます。