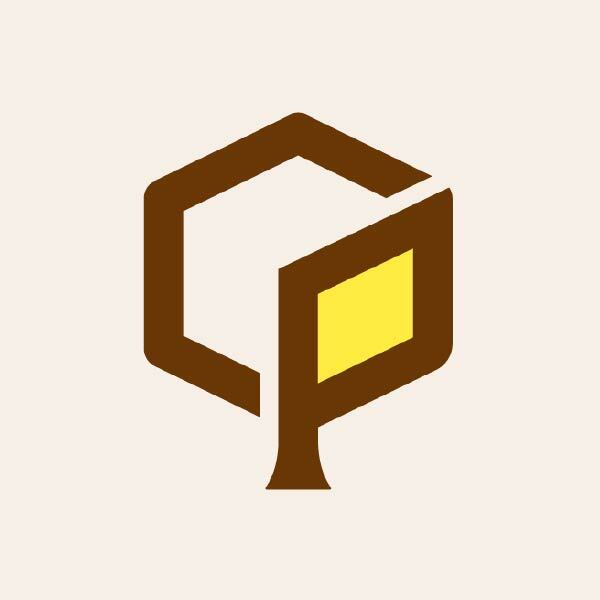過去問については、直近の年度のものは人事院のHPに掲載されています。また、古い年度のものについては、情報開示請求を行うことで入手可能ですが、請求してから到着までに1か月以上かかる場合もあるため、早めに取り寄せることをおすすめします。
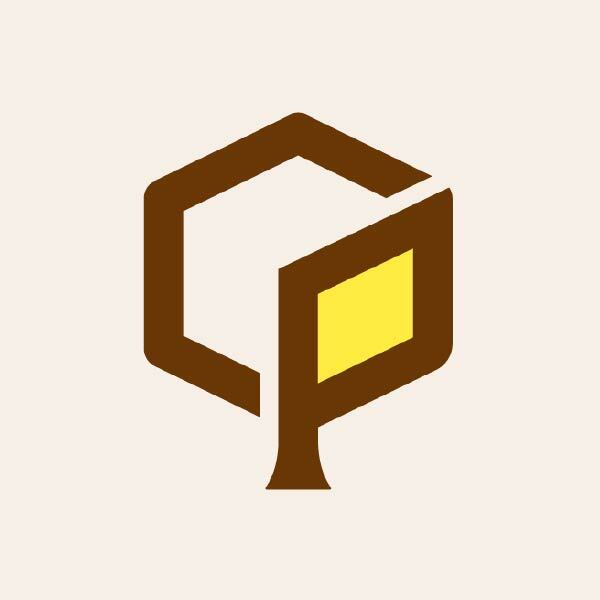
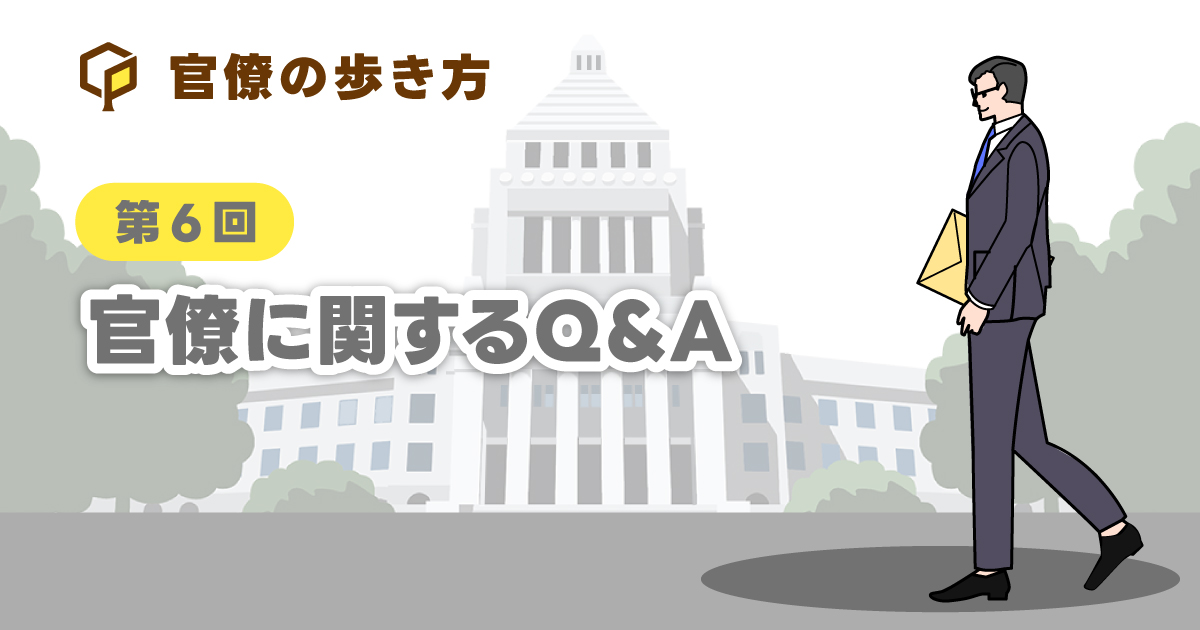
前回までは、官僚の仕事内容や年収、キャリアパスのほか、選考プロセスについても解説してきました。
今回は、官僚に関心のある学生からよく挙がる疑問にお答えしていきます。実際の働き方や試験対策に関して深く知ることで、官僚として働く具体的なイメージを持つことができるでしょう。
省庁に勤務している国家公務員全体の平均残業時間は、月31.8時間(人事院公表)で、民間企業の平均である月21時間(doda調べ)よりも高い水準です。特に、国会対応や予算編成、災害対応などの重要な局面では、深夜までの勤務が続くこともあります。
このように、官僚の仕事には厳しさが伴うのは事実ですが、これは国を支えるという重要な仕事を担っていることの表れと言えるでしょう。
とはいえ、すべての時期で激務というわけではなく、業務量には波があることがほとんどです。また、最近ではテレワークや時差通勤などの働き方改革も浸透しつつあり、職場環境の改善も少しずつ進んでいます。
若手職員は、資料作成の補助、関係各所との連絡業務など、どれも政策の根幹を支える重要な業務ではあるものの、いわゆる“縁の下の力持ち”的な仕事を担当することが多くなります。
しかし、一見地味に思える業務でも、こなしていく中で、着実に力がついていきます。ミスなく仕事を行う正確性、想定外の事態にも臨機応変に対応する柔軟性、困難な状況でも最後までやり遂げる粘り強さ――こうした力は、どのような業界でも通じる普遍的なスキルです。このように様々な力が身につくことは、実は官僚の仕事の隠れた魅力と言えるでしょう。
また、省庁によっては、若手が政策提案に挑戦できる機会を設けている場合もあります。例えば、文部科学省では「Policy Making for Driving MEXT」、農林水産省では「政策OpenLab」のような、有志の若手職員がアイデアを出して議論することで、新たな政策を作る枠組みを設けています。このような取組に積極的に参加していくことも、やりがいを高めるための一つの選択肢になるでしょう。
国家総合職における女性採用比率は年々上昇しています。2025年4月に採用された国家総合職の女性比率は36.8%を記録し、過去最高を更新しました(内閣人事局公表)。
また、育休以外にも時短勤務の制度が整っており、子育てをしながら働いている女性も少なくありません。加えて、女性の管理職への登用も徐々に進んでおり、女性が長く働ける環境になっていることが伺えます。
とはいえ、省庁によって風土には差があります。実態を知るには、説明会・座談会などで志望する省庁の職員に話を聞いてみることをおすすめします。
入省から定年付近まで勤める場合、地方や海外へ数回程度の赴任をすることが一般的です。ただし、省庁・職種などによって転勤の頻度やタイミングには差があります。
例えば外務省では、入省3~4年目には留学、5~6年目には在外公館での勤務というように、海外に赴任する時期が決まっています。また、環境省の自然系職員の場合は、全国にある国立公園などと本省の間を行き来するキャリアが一般的です。
志望する省庁での詳しい事情については、こちらも職員に直接聞いてみるのがよいでしょう。
中央省庁では、在職10年未満の若手を対象に「行政官長期在外研究員制度」が設けられています。”人事院による選考”と”留学先の大学院の入試”に合格することで、海外大学院へ留学することができ、費用は国が負担します。
なお、留学期間中または帰国後5年以内に退職すると、留学費用の返還が求められることには注意しましょう。この制度は、個人の学びのためではなく、あくまで留学で得た知見を政策に還元するための制度であることは、認識しておく必要があります。
大学4年生の春の試験に照準を合わせている学生が多く、それに向け、1年前となる大学3年生の春頃から本格的に対策を始める人が多くなっています。ただ、志望がすでに固まっている場合は、もう少し早い大学2年生の秋~冬頃から準備しておくと安心材料になるでしょう。特に、試験科目と重なる分野を大学で専攻していない人は、専門試験の勉強に時間がかかる可能性が高いため、早いうちからの対策がより大切になります。
試験の出題範囲が非常に広いため、参考書を読みながら網羅的に暗記するような方法ではなく、演習中心の効率的な勉強が不可欠になります。
数的処理・文章理解・資料解釈・自然科学・人文科学・社会科学など多岐にわたる分野が出題されます。まずは、過去問を1年分解いてみるなどして、対策に力を入れるべき苦手分野を特定しましょう。
文系の受験者にとっては数的処理や理科分野が、理系の受験者にとっては人文科学や社会科学の問題が難しく感じられることが多いです。苦手意識のある分野は早めに着手し、市販の分野別問題集を使って繰り返し演習するのが効果的です。
法律・経済・工学・デジタルなど、自分が選択した試験区分の専門知識が問われます。過去問の演習が最も重要で、頻出テーマや出題傾向をつかむことが合格への近道です。
ただし、過去問の正答は公表されていないため、参考書やインターネットを活用しながら、自力で正解と根拠を調べる必要があります。その際、選択肢の正解を特定するだけでなく、「なぜ他の選択肢が誤りなのか」を説明できるレベルまで理解を深めることがポイントです。
課題について自分なりの立場で政策提案を行うことが求められます。過去問を活用して、時間を計って書く→添削を受ける→書き直すというサイクルを繰り返すと効果的です。
答案の添削は、大学の学内講座やキャリアセンター、予備校などで依頼が可能です。また、時事的な社会課題が多く扱われるため、日頃から新聞や白書などに目を通し、自分なりの考えを持っておくことも大切でしょう。
過去問については、直近の年度のものは人事院のHPに掲載されています。また、古い年度のものについては、情報開示請求を行うことで入手可能ですが、請求してから到着までに1か月以上かかる場合もあるため、早めに取り寄せることをおすすめします。
「官僚の歩き方」では、全6回にわたって、官僚の仕事の魅力やキャリアパス、実際の働き方や採用までの流れ、そして試験対策のポイントまで、さまざまな内容を解説してきました。
官僚の仕事は、国の将来を担うという責任の重さがあり、厳しい局面も少なくありません。また、選考に向けた準備にも専用の対策が必要で、ハードルの高い面があります。それでも、国を支えるという唯一無二のやりがいを感じられることは、官僚の大きな魅力です。また、実は若手でもアイデアを出せる場面があり、経験を積む中でどんな仕事にも活きるスキルを身につけることができるのです。
こうした仕事の実情を知ることで、どこか縁遠く感じていた「官僚」という選択肢が、少し身近に感じられるようになっていれば嬉しいです。興味を持った方は、ぜひこれからも情報収集を続けてみてください。特に人事院や各省庁が開催する採用説明会、OB・OG訪問などを通じて、実際に働いている人のリアルな声に触れてみると、より理解が深まるでしょう。